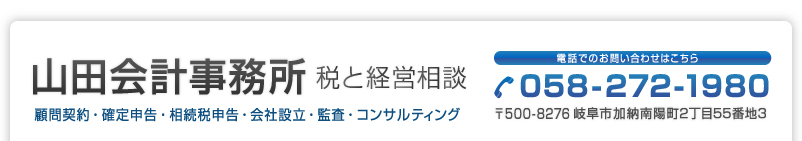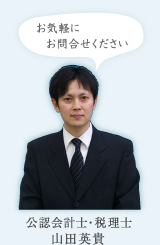Q : 役員との間で金銭貸借契約を交わす際の留意点は?
A : 会社の資金繰りが苦しい際に、役員が会社に資金を融通するということはよくある話です。逆に、役員に対して会社が金銭を融通するということもあります。
この場合も、利息を付けるなど、一定の要件を満たさなければ、思わぬ税金を支払うこととなりかねませんのでご注意ください。きっちり金銭消費貸借契約書を作成し、記載しておきましょう。また、取締役会において金銭消費貸借契約書の承認を得ておきましょう。
■役員へ金銭を貸し付けるケース
住宅を取得する、もしくは子供の学資にあてたいなどの理由で、会社が役員に対して金銭を融通する場合、無利息、または極端に低利で金銭を貸し付けしていると、世間相場との差額は役員報酬とみなされ、役員本人には、所得税が追加で発生することになります。一方、会社で同額を損金処理できるかというと、そうはいきません。
したがって、役員への貸付は、必ず利息をとるようにしましょう。
税法で定められている利率は、次のいずれかです。
① 会社が金融機関等から借り入れて役員に融資した場合
・・・その利率以上
② その他の場合
・・・前年11月の公定歩合+4%以上
会社が金融機関から借入が可能であれば、①のほうが有利となるでしょう。
■役員から金銭を借りるケース
上記とは逆に、会社が役員からお金を借りる場合、会社が利息を支払わなかったとしても、特に問題となることはありません。それだけ損金(費用)が減って税金が増えるわけですから、税務署はとやかく言いません。
しかし、適正な利息分を役員に支払えば、それを会社の損金にすることが出来ます。
ここでいう適正な利息分とは、次のいずれかを言います。
① 役員が金融機関等から借り入れて会社に融通した場合
・・・その利率未満
② その他の場合
・・・前年11月の公定歩合+4%未満
不当に高い利息を支払った場合、適正額を超えた分が役員報酬(賞与)とみなされますのでご注意ください。
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)